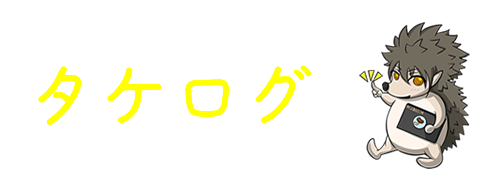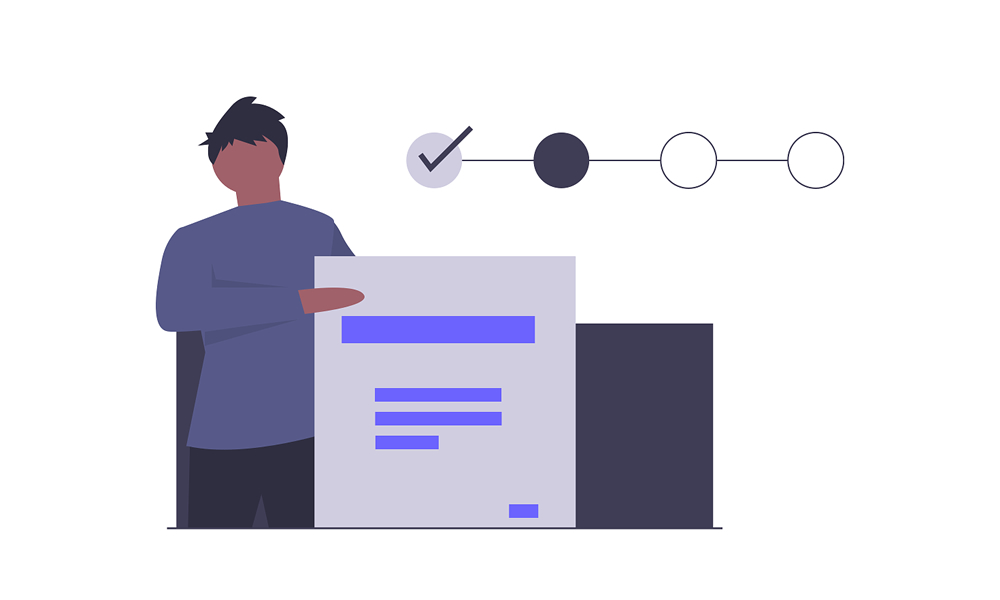今回は提案を通しやすい提案書の作成方法を解説いたします。提案が中々通らない人は必見です。

読んだ後から即実践できます
こんにちは。Webディレクターのタケです。
今回は「通りやすい提案書」の作成方法を解説したいと思います。
長い時間をかけて提案書を作成しても提案が通らなかった経験って皆ありますよね?
今回の記事を読んでいただければ提案が通りやすい提案書を作成することが出来ます。
参考になったら嬉しいです。
それではどうぞ
通りやすい提案書:クライアントの手間を減らす

説明をするにあたり、これから皆さんに協力していただきたいと思います。
ここから先はご自身に置き換えて想像してみてください。
ある日あなたはクライアントから新しいサービスを展開したい。という相談を受けました。
打ち合わせの予定も組めたので後は提案するだけです。
どうでしょう。良い提案書を作ることが出来ましたか?
準備OK!と行きたいところなのですが、ちょっと待ってみてほしいです。
あなたが作ったその提案書に漏れや抜けはありませんか?
・導入と動作の検証期間は?
・問題無く運用できますか?
・どれだけの効果が見込めますか?
・全体のスケジュール感は?
・他のツールと比較しましたか?
いやいや、しっかり書いてます!
という方は大丈夫です。
効果が期待できるツールを使いたい!という気持ちだけ先行してツールの費用と機能面だけ書いた人はいませんでしたか?
心当たりがある方は誰も見ていませんが右手をスッとあげましょう。
もしクライアントから
これを聞かれて回答できないとその後のやり取りが多くなってしまい、クライアントの気持ちが冷めてしまいます。
クライアントが「やる」か「やらないか」だけ判断できる提案書にしましょう。
ただ、それらを抑えたとしてもまだ提案書としては甘いので、更に提案を通しやすくする工夫をしましょう。
解説します。
通りやすい提案書:捨て案を複数用意する
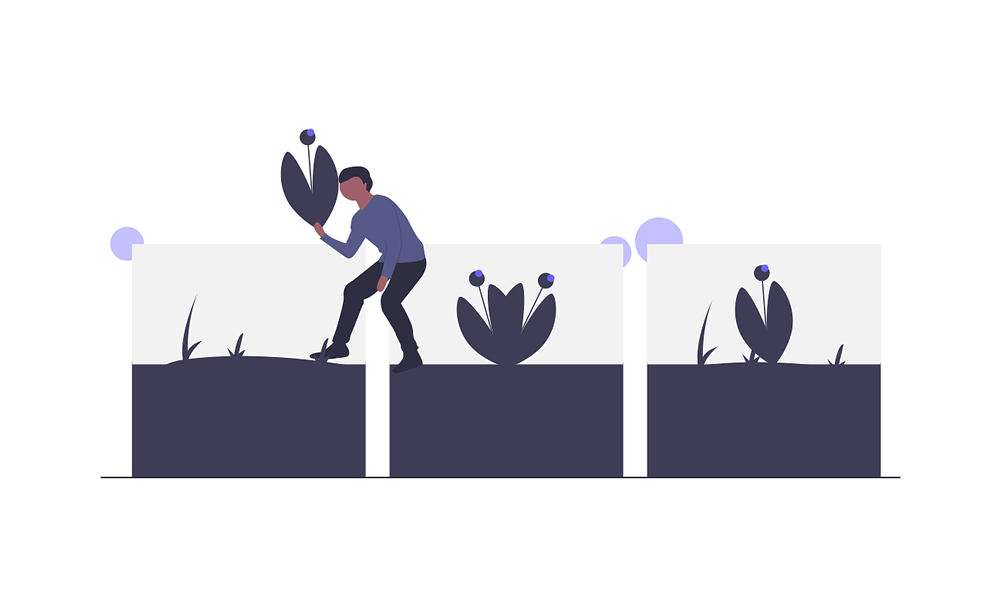
本当に提案したいものが1つしかなかったとしても他の案を複数用意しましょう。
クライアントの要望を満たせそうなツールがA・B・Cの3つあったとします。
ここでは一旦コスト面を無視して考えてみてほしいです。そして導入後の見込める効果はA・B・Cどれもさほど変わりません。
ではその中であなたが運用した際に1番楽になるツールを1つ見つけましょう。
そのツールに関してはよりメリットが伝わるように、それ以外に関しては少し力を抜いた提案書にしましょう。
そしてA・B・Cそれぞれのメリット・デメリットの説明を打ち合わせの際に行います。
その際に
それに比べBは導入が早く済み、操作性も優れておりますので今後の運用面を考慮するとBがお勧めです。
Cに関しては他と同様の効果を見込めますが導入までの手続きが少々複雑でございます。
なので個人的にはBの導入を推奨いたします。いかがでしょうか。
といった具合にBというツールは他に比べて魅力的なんだと伝わるように説明しましょう。
そして必ず相手に判断を委ねます。
ここがポイントです。
消去法で相手はBを選択するしかないのにも関わらず自分の判断でBを選択したと錯覚します。
クライアント自身の判断で選んだ提案はそうそうひっくり返りません。
あとからやっぱりあの案件無し!とは簡単にはならないです。
言い方はちょっと乱暴ですが馬鹿正直に1つの提案で勝負するのと、より魅力的に伝えるこの方法、どちらの提案が通りやすいか一目瞭然ですよね。
自分の提案を通しやすくするために今日から工夫してみましょう。
最後に:これで提案書作りはOKです

いかがでしたか?
簡単にまとめると
相手に聞かれて困ることは隙間なく潰しておく。「やる」か「やらないか」だけ考えてもらえればいい状態にする。
通したい提案をより魅力的に伝えるために複数捨て案を用意し比較対象にさせ消去法で相手に選ばせる。
1番ダメなのはたった1案しか用意せず、全体のスケジュール感も全体のコストも不透明で提案が通らなかった時です。
この人の提案に魅力も感じないし、やり取りも多いし嫌だなぁ
と思われてしまうと仕事が増えないので提案書は注意して作成しましょう。
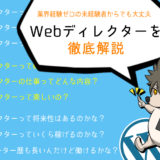



参考になったら嬉しいです!即実践できる内容なので試してみてください!